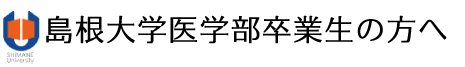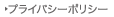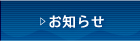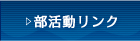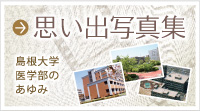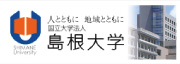田中 志幸(第14期)
研究時代の思い出
医療法人水清会
水島第一病院 内科部長
田中 志幸(第14期)

同窓会の皆様、ご無沙汰しております。14期の田中志幸と申します。早いもので卒後26年が経過しようとしていますが、皆様ご壮健にされていることと存じます。私はキャリアの半分近くを、基礎研究で過ごしました。今回は、その頃の思い出を中心にご報告したいと思います。
卒後、岡山大学第二内科に入局しました。卒後研修は一年目に呉共済病院、二年目にKKR高松病院と第一線の研修病院で研鑽を積むことが出来ました。この貴重な2年間が、長い臨床のブランクを挟んだ今の私の支えになっていると感謝しております。
3年目を迎える時、基礎研究にも興味を抱いていた私は、当時の原田実根教授の勧めで岡山大学寄生虫学教室(現、免疫学教室)の故、中山叡一教授の門を叩くことになりました。最初の研究テーマは癌の免疫治療の標的になり得る細胞性免疫抗原を探索することでした。マウスの腫瘍細胞の膨大なcDNAライブラリーから有望な遺伝子を見つけては、細胞傷害性T細胞の反応性を確かめる気の遠くなるような作業を来る日も来る日も続けました。
数年を費やした後、私の与えられた細胞の抗原は教室の別の先生が別の方法論で抗原を特定されました。焦った私は中山先生にずいぶんと我が儘を聞いていただき、独自のテーマを始めました。それが、抗腫瘍DNAワクチンの実験でした。マウス腫瘍モデルの既に特定された腫瘍抗原遺伝子をプラスミドに組込み、大腸菌に導入して大規模にプラスミドを抽出してマウスの横紋筋にエレクトロポレーションという方法で発現させました。このマウスに元の腫瘍細胞株を接種して、最終的にはマウスに抗腫瘍免疫を惹起して腫瘍を拒絶させることが出来ました。この研究で、7年にも及んだ大学院生活を遂に卒業することが出来ました。この研究には、エレクトロポレーション法を私に指導してくださった、当時大阪大学第二外科の山田先生、装置の購入資金を研究費から捻出してくださった免疫学教室の小野先生のお力添えが無ければ実現しませんでした。この場を借りて、感謝申し上げます。
核酸ワクチンという発想は古くからあったものの長くマイナーな立ち位置に置かれていましたが、皆さんもご存じのごとく今日メッセンジャーRNAワクチンとして日の目を見ることとなりました。新型コロナのDNAワクチンも、阪大・タカラバイオのチームで実用化に向けた開発がされています。
私は大学院の終わり頃に国立療養所長島愛生園に週数日勤めていた事から、ハンセン病の免疫に興味を持つようになっていました。たまたま岡山大学に講演に訪問されていた、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でハンセン病と結核の感染免疫を研究されていたRobert L. Modlin教授に出会い研究留学の許しを得る事が出来ました。この頃、今の妻と結婚しましたが、結婚していきなりの渡米でずいぶん苦労をかけてしまいました。3年間の留学生活で研究の傍ら、多くの旅行もし、貴重な体験をすることが出来ました。研究では抗原抗体複合体が未熟な樹状細胞を誘導することで自己免疫を誘導しうることを示し、纏めることが出来ました。
帰国後、京都大学ウイルス学研究所に特定助教として1年間お世話になりましたが、病を得て基礎研究者としての道を諦めました。この時、現、医療法人水清会理事長の平木章夫先生に窮状を救って頂き、臨床医として再出発する事が出来ました。
現在は、岡山県倉敷市の水島第一病院に在職13年目となり、内科部長の一人としてコロナ対応を含む感染症対策や、摂食嚥下医療とNST活動等を担当して多忙ながらも充実した日々を送っております。特にコロナ禍が始まってからは、感染免疫の知識や論文検索の経験が役に立つ事が多くあります。現在に至るまで大きな回り道をしましたが、後悔は無く、お世話になったり、御迷惑をおかけした多くの方に感謝で一杯です。
末筆ながら、皆様の御多幸をお祈りして筆を擱きます。