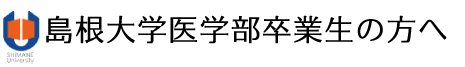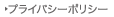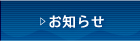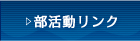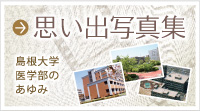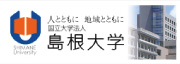坂上 憲史(第7期)
私の4つのふるさと
さかがみ眼科・皮膚科 院長
坂上 憲史(第7期)
私は1988年に島根医大を卒業し、大阪大学眼科へ入局。2011年に大阪府豊中市千里中央にて、13期生の妻、麻衣子と「さかがみ眼科・皮膚科」を開業して現在に至っています。
皆さんにとって「ふるさと」とはどういうものですか。出生地、先祖の住んでいたところなど、いろいろな定義はありますが、私は何かの出発点になった場所かと思っています。そういう意味では、私には4つのふるさとがあります。
第一のふるさとは、もちろん私が生まれ育ち、今も住んでいる大阪府豊中市です。千里中央は千里ニュータウンの中心地で、交通の便が良いうえに、公園や緑地帯も多く、とても住みやすい街です。
第二のふるさとは、島根県出雲市です。硬式テニスに明け暮れる6年間でしたが、島根医大の6年があったからこそ、医師になることができ、現在の自分があるのです。とても感謝しています。まさに「医の扉」を開けてくれた「医師のふるさと」が出雲市です。また、この地でテニス部の後輩であった妻と知り合い、「人生の扉」を開けてくれたところといっても過言ではないでしょう。
第三のふるさとは、愛媛県松山市です。阪大眼科へ入局したのち、7年目に関連大学である愛媛大学へ転勤となりました。私は眼科の中でも網膜剥離などを扱う網膜・硝子体部門に興味を持っていました。しかし、大阪では競争相手も多く、「自分が、自分が・・・」と積極的に前に出るタイプでもないので、何となくくすぶっていました。ところが、愛媛では網膜・硝子体部門のチーフを任されるようになり、状況は一変しました。網膜剥離の手術に明け暮れる日々が続き、眼科手術の技術のみならず、周り人々の信頼をも築き上げられた、まさに「眼科手術のふるさと」ともいうべきところです。
第四のふるさとは、米国ミシガン州のアナーバー市です。卒後9年目に愛媛大学からミシガン大学眼科へ3年ほど留学させてもらいました。ピューロ教授は網膜グリア細胞を長年研究されている先生で、阪大眼科からは代々留学生が派遣されており、私で5代目でした。当初は先生と私の二人だけの小さな研究室でした。ピューロ先生は眼科医でもあり、日常診療をしながら研究されているとても紳士的な先生です。家族と過ごす時間をとても大切にされ、仕事以外に先生から学ぶことも多かったです。グリア細胞ではなく、私は新しい研究にチャレンジすることになりました。網膜周皮細胞(ペリサイト)という毛細血管の外側を形作っている細胞の研究です。糖尿病網膜症では最初にペリサイトが選択的に消失することが知られており、パッチクランプ法という電気生理学的手法を用いて、この細胞のイオンチャネルの糖尿病による変化を調べるのがテーマです。ティッシュプリント法という網膜から毛細血管を組織ごと取り出す方法を自ら開発し、ペリサイトにガラス管で作ったマイクロピペットを刺して、電位の変化を調べる日々が続きました。世界的にもこの研究は進んでおらず、苦難の連続でした。安定したデータを測定できるまで2年。何度もあきらめかけましたが、ピューロ先生の人柄と、たまに得られる素晴らしデータに励まされ、3年目には論文を書けるほどになりました。その間、同僚が増え、4期生の児玉達夫先生(先端がん治療センター准教授)が留学してこられ、研究のノウハウを教えていただきました。ありがとうございました。
ミシガンでもう一つ出会ったのがアイスホッケーです。詳細は別の機会があればお話ししますが、スケートもしたことがなかった私がアイスホッケーに魅せられ、英語の練習も兼ねてスケートの個人レッスンを受け、地元の初心者リーグでアメリカ人のチームメイトとともに戦いました。コーチになるためのセミナーにも積極的に参加して知識だけは一人前になり、帰国後は愛媛大学アイスホッケー部の監督をやらせていただいています。監督になって、今年で20年。インカレへ4回出場しました。「研究とアイスホッケーのふるさと」。それが米国ミシガンです。
4つのふるさと、そしてそこで出会った多くの人々に支えによって、充実した日々を送ることができています。
最後になりますが、私が大切にしてきたことは、「となりの芝生が青く見えても、気にせずに自分がやるべきことをする」、「まじめは必要条件だが、十分条件ではない。忙しいときほど立ち止まってゆっくり考える時間を持つ」です。何かの参考にしていただけば幸いです。